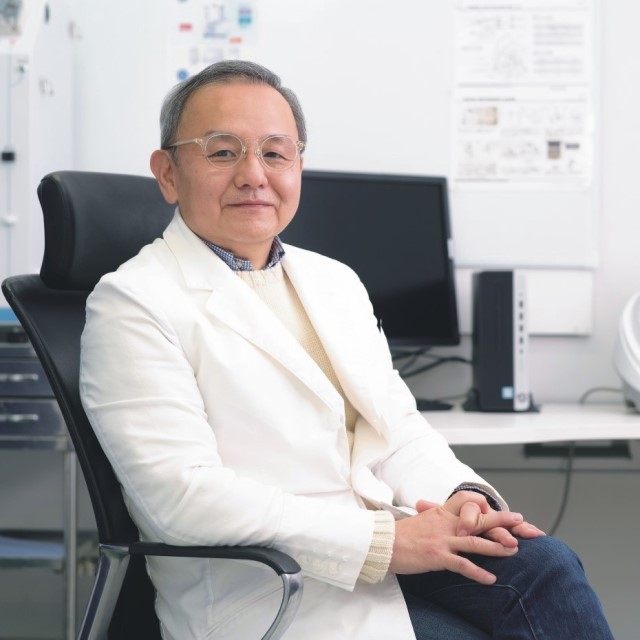令和5(2023)年の1月初旬、外食産業関係者のみならず、食に携わる人々、食通たちに大きな衝撃を与えるニュースが、海外から飛び込んできた。世界一とも称されるデンマークのレストランが、1年後に営業を休止するというのだから、誰もが驚いた。世界中の食通たち垂すい涎ぜんの的であり、もっとも予約が取りづらいレストランがなぜ?
その疑問に答えていわく、「過酷な労働時間と激しい職場文化を持つ高級店は限界点に達している」。つまりは持続不可能だというのが、通常営業を終える理由だというのだ。もう少しかみ砕いて言えば、スタッフたちにまともな給料を払えば、収益が上がらないからやめる、ということなのだろう。
このレストランに限らず、世界に名をとどろかせる店は、研修生という名目で、無給、もしくは最低に近い労賃しか払わずに働かせている。長くそれが習慣化し、スタッフの側もそれを当然として、将来の夢のために過酷な条件を受け入れてきたのである。
しかしながら世のなかは変わる。持続可能な社会、という言葉が声高に叫ばれ、SNSの発展もあって、労働者も社会も旧来のシステムにNO!を唱え始めた。やむなくレストラン経営者もこの声に応え、労働に見合った給与を支払うことにしたが、それを続けると利益が上がらないことに気付き、営業を休止すると発表したわけである。
このニュースを聞いて、反応が大きくふたつに分かれたのは興味深い。
ひとつはレストラン側の「共通の問題であり、解決するためにはまず料理の価格を上げ、ロボットやAIを導入すべき」という意見で、有名レストランや高級割烹の主人たちは、これに賛意を示した。 一方で客側の意見として、「高級レストランには縁がないから、どうでもいい」「ロボットを使った料理など食べたくない」と、否定的な意見が目立った。
飲食業に限らず、伝統産業や、伝統芸能に携わるひとたちは、多かれ少なかれ、同じような環境で育ってきたはずで、それを当然のこととして受け入れてきた。研修であるならば、本来は研修生側が月謝なりの形で謝礼を払わねばならず、労働であるならば、当然ながら雇用する側が正当な賃金を払わねばならない。
相反する二面性を、どう解釈するかで、正反対の答えが出るのではないだろうか。旧来の手法が間違っていたので、今後正していくべきなのか、それとも従来どおりでいいのか。答えはまだまだ出そうにない。
下世話な話だが、この問題で気になるのは料理の値段だ。 人件費もさることながら、最近は原材料費や光熱費の高騰も大きな問題となっている。毎月のように食品の値上げが報じられ、家計を圧迫しているという声も高まっている。そんななかで外食費を抑える傾向も出てきているから、飲食店も簡単に値上げなどできず、悩ましい問題となっている。
くだんの料理人代表は、ディナーが60万円になればすべて解決できる、と主張したが、現実的にはむずかしい話だろう。
営業休止を発表したデンマークのレストランが、期間限定で京都のホテルに出店することになった。その予約は瞬時に完売になったと言い、料金はドリンクを含めた税サ込みでおよそ850ユーロだったそうだ。これを書いている時点では、1ユーロが140円前後だから、ざっとひとり12万円ほどだ。庶民感覚からすれば、飛び抜けて高額に感じるが、富裕層からみれば、世界一のレストランの料理として、妥当な価格なのだろう。
近年よく言われるのは、日本の外食は安すぎる。それは低賃金を強いているからで、賃金を上げ、それに合わせて料理の値段も上げるべきだという主張を耳にする機会が増えて来た。しごくもっともだと思う半面、それによってラーメンが1杯2000円になったら、はたして食べに行くだろうかとも思う。
外食の値段はどうあるべきなのか。この論争はまだ始まったばかりだ。
柏井壽 かしわい・ひさし
1952年京都市生まれ。京都市北区で歯科医院を開業する傍ら、京都関連の本や旅行エッセイなどを数多く執筆。2008年に柏木圭一郎の名で作家デビュー。京都を舞台にしたミステリー『名探偵・星井裕の事件簿』シリーズ(双葉文庫)はテレビドラマにもなり好評刊行中。『京都紫野 菓匠の殺人』(小学館文庫)、『おひとり京都の愉しみ』(光文社新書)など著書多数。