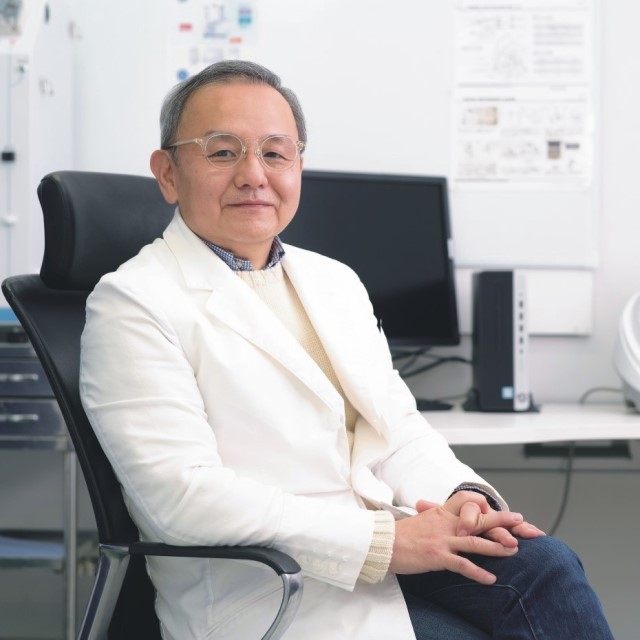梅雨どきになると、何もかもが黴(かび)臭くなるような気がして、いささかなりとも食欲が落ちる。
春と夏の端境期だから、旬の食材も乏しい。海も豊穣とは言えず、かと言って、春の息吹を感じさせるような土の恵みも、すでに終わってしまった。
そこはしかし、うまくしたもので、日本には、この時季ならではの味わいがある。しかもそれは、彼の北大路魯山人(きたおおじろさんじん)を筆頭に、多くの食通たちが憧れをもって語る食材だ。
それは別名を多く持つ川魚のこと。年魚。香魚。川魚の貴公子。さまざまな異名を持つ鮎こそが、初夏から盛夏にかけて旬を迎える川の幸。目に青葉、の季節になると、海では初鰹となるが、山里に分け入る太公望は、決まって鮎を思い浮かべる。
四方を海で囲まれた日本はまた、山から流れ出る川が、縦横無尽に流れを作る国でもある。海に近い河口でも鮎は釣れるが、やはり奥山の急峻な流れに棲む鮎にこそ心魅かれる。
川によって解禁日が異なるのも、太公望の心を浮き立たせるのだろう。待ちかねて、といった風に釣り糸を垂れ、友釣りという類いまれな仕掛けで鮎を釣る。厳密に決められた解禁日を正しく守るのも、年魚である鮎に敬意を払えばこそ。
あるいは、琵琶湖の稚魚を、日本中の河川に放流し、それが育つのを待つ。
そんな決まり事がある「食」が他にあるだろうか。つまり鮎は、ただ食材という観点だけでなく、古くから伝わる仕来りやマナーに則(のっと)って、収穫される魚という意味で、他に類を見ない、極めて日本的な食材なのである。
そして何より、鮎という魚が他と異なるのは、語るべきことが山ほどあるということ。
例えば名所。日本各地には鮎の名所と呼ぶべき川があり、お国自慢よろしく、どの川もが日本一を謳(うた)う。我が川の鮎が一番旨(うま)い。
あるいは、その質や大きさ。天然物に限ると断じる食通が居る一方で、巧く養殖した鮎の方が旨いと言い張る向きもある。小ぶりがいい、たっぷり大きい方がいい、などなど。
さらには焼き方から食べ方に至るまで、詳細にわたって魯山人も書き残している。鮎には語るべきことが山のようにあり、独特の〈食語〉もある。
まず語られるのは、天然か養殖か。しかし近頃は、京都の割烹辺りでも、〈半天〉という呼び名の養殖モノが幅を利かせている。
〈半天〉とは、読んで字のごとく。半分天然という意。
養殖した鮎を、適度な寸法に育ったところで、河川の水を張った生簀(いけす)に放ち、川魚らしい香りを付ける。最近では苔(こけ)の生えた石を沈め、それを餌にさせて、より一層、天然の味に近付ける。
少し太めの親指ほどの厚み。中指を幾らか超える長さの鮎。完全な天然モノでそろえるのは難しいが〈半天〉ならそれがかなうというわけだ。
この大きさなら、じっくり焼いて骨まで火を通せば、頭からガブリとやれる。面倒な骨抜きなど不要だ。
鮎料理は塩焼きに限る。食通たちの一致した意見だ。魯山人が言う。
「鮎どころでは、客の顔を見ると、待ってましたとばかり、その鮎を塩焼き、魚田、照り焼き、煮びたし、雑炊、フライと、無闇に料理の建前を変えて、鮎びたりにさす悪風がある」(『魯山人味道』中公文庫)として多彩な調理法を戒めている。
小指ほどの稚鮎なら、天麩羅という手もなくはないし、腸を塩辛にしたウルカも酒のアテにはいい。しかし成魚として鮎を食べるなら、塩焼きに限る。それも焼き立てを頰張るのが最良。
鮎の塩焼き。簡単そうに見えて、これが実は難しい。多くの料理人が見栄えを優先して、焼きを浅くするが、これは感心しない。化粧塩を施しすぎるのもよくない。焦げる寸前まで、じっくりと焼くのがいい。
生きた鮎に串を打ち、炭火で炙る。鮎は悔しさからか、より顔付きを鋭くする。口を開き、尖った歯を見せ、魚体を捻る。まさに生命をいただくという感謝の念が湧く瞬間だ。鮎は川の恵みを食べ、人はその鮎を食べる。食の輪廻。生命の循環。
日本には、〈食む(はむ)〉という〈食語〉がある。
鮎は好んで苔を食む。そしてその苔の青い香りが腸に染み付き、苦みと共に、西瓜や胡瓜のような香りを鼻腔に残すのである。香魚と呼ばれる所以(ゆえん)。いい苔を食む鮎は必ず旨い。
清流であればあるほど、急峻な流れであればこそ、苔の香りは清らかで青い。人間は苔を食べたことがないので分からないが、きっとそうなのだろう。
川底の岩にこびり付いた苔を食もうとすれば、自然と口先を尖らせることになる。鮎は口先が鋭角であるほど、しっかりと苔を食んで育った証拠。魚体もまた然り。縄張り意識の強い魚ゆえ、生存競争は厳しい。急な流れに負けず泳ぎ、いち早く苔を食むためにはスリムな魚体でなければならぬ。鮎選びの要諦(ようてい)である。
食む。先月ご紹介した〈食べる〉と好一対をなす言葉。食む、と言って、多くに馴染みが深いのは、
――瓜食めば子ども思ほゆ 栗食めばまして偲はゆ いづくより来りしものぞ 眼交(まなかひ)に もとなかかりて、安寐し寝さぬ――
山上憶良の歌だろうか。ここで〈食む〉は〈食べる〉を、より具体的に〈嚙む〉ことを主として、言い表しているように思える。瓜と栗。韻を踏みつつ、その歯応えの違いを巧く対比させる。〈食べる〉よりもプリミティブな、生きるための営みを〈食む〉いう言葉で言い表している。
瓜はパキッと嚙み切れるが、栗は嚙むほどに歯に纏わり付き、瓜のような青臭さではなく、滋味深い甘みを舌に残す。
旨いものを子供に食べさせてやりたいという親心を切々と詠う。
さて、その〈食む〉。実は京都の夏に欠かせない食べ物と、密接なつながりを持つ言葉なのである。京都の夏の風物詩とも言える、あの食である。次回はその話をしよう。
柏井壽 かしわい・ひさし
1952年京都市生まれ。京都市北区で歯科医院を開業する傍ら、京都関連の本や旅行エッセイなどを数多く執筆。2008年に柏木圭一郎の名で作家デビュー。京都を舞台にしたミステリー『名探偵・星井裕の事件簿』シリーズ(双葉文庫)はテレビドラマにもなり好評刊行中。『京都紫野 菓匠の殺人』(小学館文庫)、『おひとり京都の愉しみ』(光文社新書)など著書多数。
※『Nile’s NILE』2013年6月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています