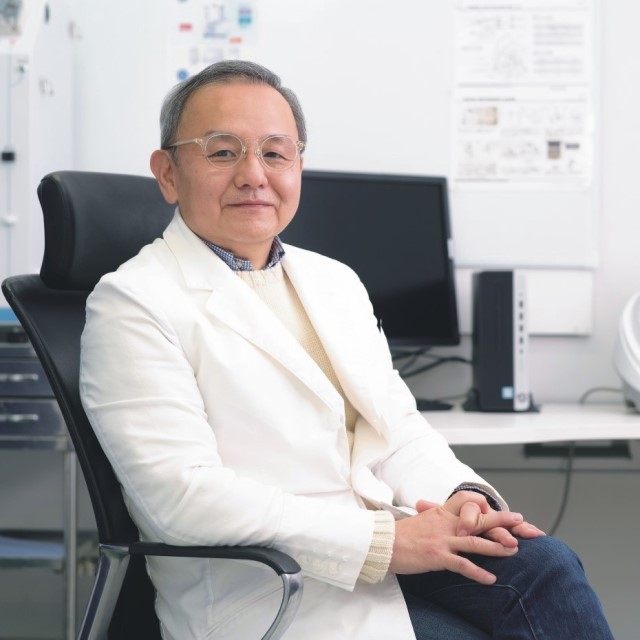久しぶりにパリに出向いた。国際商業会議所(ICC)の中でも中核的な意味合いを持っている組織「G20 CEO アドバイザリー・グループ」の本会合に出席するためである。議長は「スウェーデンの3分の1を所有している」と噂されているマーカス・ワレンバーグSEB会長が務めている。このグループには当然のことながら「入りたいです」と言ってすぐに入れるわけではない。
と言ってもどこぞの怪しげな「紳士倶楽部」とは違う。ICCは第1次世界大戦の反省を踏まえて創られた国際民間組織である。最近では国連にもオブザーバーの地位を獲得するなどかなり旺盛な活動を展開しているが、中でも最も力を入れているのが新しいグローバル・ガバナンスのための仕組みである「G20」に対する知的貢献なのである。
要するにこういうことだ。――政府間会合であるG20では政治や外交、そして安全保障の話もするが、元来これはリーマン・ショックをどのようにして収拾させるか、その一点に絞り込んで急ぎ立ち上げられた会議体であったという経緯を持っている。無論、現在では小康状態にある金融マーケットが主たる議題というわけではなく、今後のグローバル経済や社会の在り方についてより広い観点から議論をする場になっている。そこに対してグローバル・ビジネス・コミュニティーの集まりであるB20が政策提言を行うわけだが、端的に言うとこのB20で形式的に議論される内容は、実のところICCが考え出したものなのである。要するに「グローバル・アジェンダ」の源流中の源流、それがICCなのであって、しかも、私が属している「G20 CEOアドバイザリー・グループ」だというわけなのだ。
簡単に書いてしまったがこれは非常に重大な意味を持つ事柄である。要するにその後、1年、3年、5年、10年、そして25年とグローバル社会全体がどのようなかじ取りをするのか、少なくとも経済・社会分野ではICCのトップ・ビジネス・エリートたちが、最初の一字を書く権利を事実上有しているからだ。ところが我が国から出席を認められているのは、私一人だけである。何とも心細い限りだが、致し方ない。なぜならば我が国ではこうしたG20を頂点とする新しいグローバル・ガバナンスの在り方が、全く理解されていないからである。
実際、私はB20のメンバーであるので、これまで財務省・外務省・経済産業省の幹部に対して、この新しい仕組みについて説明を試みたことがあるわけだが、その度にこう彼らは一様にのたまわったのだ。
「勝手に議論して勝手に政府に“政策提言”なるものを押し付けてくるとは。なんとけしからん連中ではないか」
しかしグローバル社会において、こうした認識は時代遅れどころか、大いなる失笑を買ってしまうほどのものであることは、ご理解いただけるのではないかと思う。そうした我が国が「2019年にG20議長国となる」ことを宣言し、認められたのである。グローバル・シーンにおける現実を熟知している私からすれば、驚天動地の出来事であったと言わざるを得ない。なぜ、我が国によりによってG20の議長役を任せるのであろうか。これについてICCの幹部と話していたところ、次のように問いかけられたのである。
「2019年に議長国を務めるニッポンはその時、何をテーマにするのだろうか」
要するにあれだけ押し黙っているニッポンにもこのタイミングだから発言権を与えよう、とりあえず聞いてやろうというのである。だが、そう仕向けられていることにも気づかず、また気づいていたとしても意識的な議論が「公論」として、この究極の問いかけについて全く行われていない我が国は「何も答えることができない」というのが、今のところ現実なのだ。
「で、ニッポンは何をしたいのか?」ぜひ、読者も考えてみていただきたい。「解答時間終了の時」は、刻一刻と迫っている。
原田武夫 はらだ・たけお
元キャリア外交官。原田武夫国際戦略情報研究所代表(CEO)。情報リテラシー教育を多方面に展開。2015年よりG20を支える「B20」のメンバー。
※『Nile’s NILE』に掲載した記事をWEB用に編集し再掲載しています