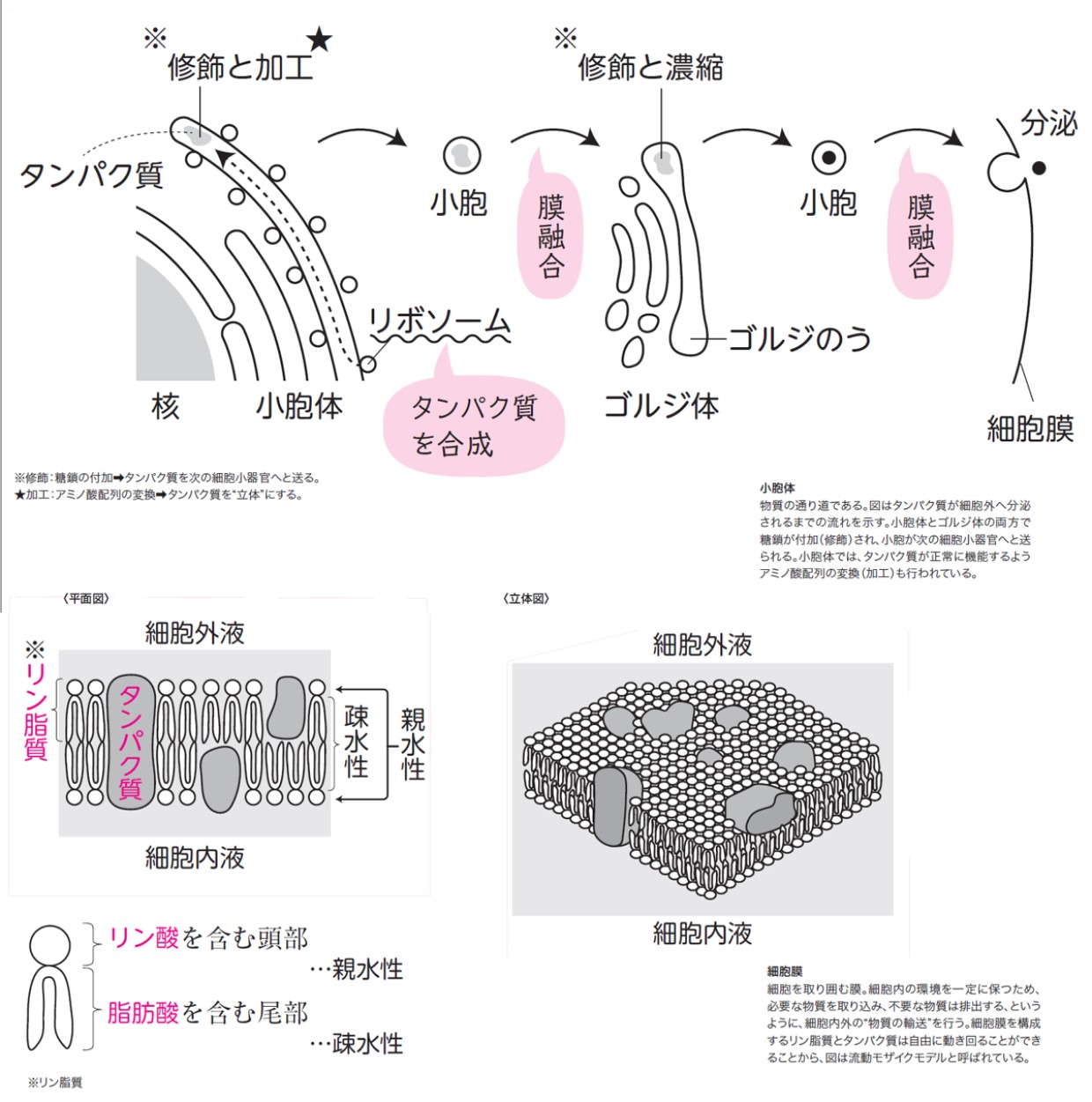
AIは細胞を超えられるか
医学の進化と並行して、人工知能(AI)にも大きな注目が集まっている。人工細胞を用いた研究が進む今、人間を凌駕(りょうが)するAIが登場する可能性はあるのだろうか。「私たちが日常で使っている脳細胞は、全体のわずか3%とも言われています。38億年かけた進化の産物であり、残り97%にはまだ活用の余地がある。AIがどれだけ頑張っても、人間を超えることは難しいと思います」
ヒトにはAIにない、感情がある。「怒りや喜びといった感情も、脳内で作られる“生きた細胞”の働き。例えば、幸せな気持ちはオキシトシンというホルモンによるもの。たくさん抱かれて育った赤ちゃんはオキシトシンが多く、幸せになりやすいというデータもあります。また、恋愛感情も鋤鼻(じょび)器官の細胞が感知するフェロモンがきっかけになります。女性はこのフェロモンに敏感で、遺伝子的に離れた相手を選ぶ傾向にあり、子孫の多様性に寄与しているのです」
一見すると唯物論の極みのような細胞研究だが、実は哲学的な側面もあるのかもしれない。「学べば学ぶほど、知れば知るほど分からないことが増えていきます。遺伝子には、まだ用途不明のものも含め2万2000個もあります。“第六感”の正体は? エビデンスはなくても効く治療とは? 生物は単なる物質ではなく、突き詰めていくと哲学に行き着くのだろうとも思います」
生物の進化と目的
「私たちは、生き延びるために進化を続けている。ダーウィンが『種の起源』で説いたように、自然淘汰を経て。そういう意味では、コロナ禍というパンデミックも人類にとって新たな進化のきっかけだったのかもしれません」
時に厳しい見解を述べつつも、そのまなざしはいつも優しい。「生物以外に興味のあること? 宇宙ですね」
細胞というミクロの世界と宇宙というマクロの世界。細胞を学ぶことで、世界を、宇宙を俯瞰できるような授業をいつか受けてみたい。
※『Nile’s NILE』2025年7月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています


















