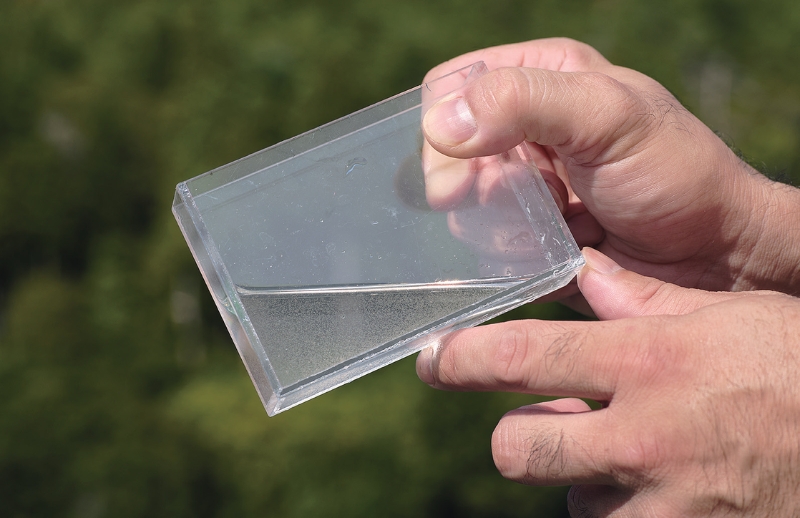気仙沼では春先になると、海の色がガラッと変わることがある。
「今年も雪代水が来たね」
と、漁師たちは言う。雪代水とは山の雪解け水のことで、緑の海水にふわりと白が混ざる。雪解け水には山の大地から溶けだしたミネラル分が豊富に含まれていて、海の植物プランクトンの養分となる。

「日本ではカキの旬は冬だと考えられていますが、気仙沼のカキが本当においしいのは4月から6月。雪代水が来てからですよ」と、植林活動や教育プログラムを実施するNPO法人森は海の恋人の代表を務める畠山信さんが話してくれた。
先代でカキ養殖家の畠山重篤さんが、前身の牡蠣の森を慕う会で活動を始めたのは平成元(1989)年。当時、気仙沼湾の環境が悪化し、大量の赤潮が発生。赤潮プランクトンを吸ったカキは身が赤く染まり「血カキ」と呼ばれて売り物にならなくなった。カキの漁場は、川が海に注ぐ汽水域につくられる。カキの餌となる植物プランクトンは、川が運んでくる森の養分によって育まれているからだ。「漁師だけでなく、川の流域に住む人々と価値観を共有しなければ美しい海は帰ってこない」。そのことを日々、海に向き合う漁師たちは知っていた。
気仙沼湾から見上げると、こんもりと茂る室根山の山頂を見ることができる。昔から海上安全や大漁祈願を行う霊峰としてあがめられてきた山だ。古来、この地の人々は森と海のつながりを体感として理解していたのだろう。信さん自身は、高校卒業後に気仙沼を出て、東京の専門学校で環境について学び、屋久島でインストラクターとして活動。気仙沼に戻った理由は、まだ環境問題が叫ばれ始めたばかりの当時の日本において「自然を相手にする一次産業の従事者が発信する言葉には力がある」と感じたからだ。
「幼少の頃から実家に出入りする研究者たちと話し、自分でも学んでみて、海だけ、森だけを保護保全してもあまり意味がないことを実感しました。それよりも一つの流域を対象に保護活動を行い、そこに教育を加えることで、相乗効果が上がるのではないかと考えたのです」
重篤さんの代から35年以上が経ち、植林活動に参加した子どもたちが、その子を連れてきたり、研究者や各省庁の役人として活動したり。木を植えて、森が育つまでには長い年数がかかるけれど、教育なら10年、20年で結果が出る。重篤さんの著作は小学校の教科書にも掲載されて話題となり、全国に仲間が生まれた。
「東日本大震災以降、巨大津波の影響で生き物が消え、誰もが『海は死んだ』と感じました。しかし今、多くの生き物がものすごい勢いで戻っているのも、思いを共にする仲間たちと森のおかげです」と、森を見上げながら信さんは語る。
平成16(2004)年には、森は海の恋人の活動をヒントに、京都大学が京都大学フィールド科学教育センターを設立し、森里海連環学という新しい概念の学問をスタートさせた。信さんたち、森は海の恋人と共同で研究することも多い。
「海水のDNAを調べた京大の研究では、川から海にかけての河口域の生物の種類を調べたところ、森の面積が大きいほど、河口の海に生息している生き物の種数が増えていることが明らかになりました。森の養分が川からだけでなく、海底湧水としてももたらされていることもわかり、活発に研究されています。また、三陸沖は世界三大漁場の一つと言われていますが、その理由に、ロシアと中国をまたぐアムール川がかかわっていることも近年の研究で判明しました。アムール川の上中流には生物多様性の宝庫である大湿地帯があり、そこで生成された栄養塩が、寒流に乗って三陸沖まで流れ着き、多彩な海洋生物を育んでいるのです」
信さんが拠点とする舞根湾には、東日本大震災で地盤がずれたことにより、新たに湿地が生まれた。この湿地に、準絶滅危惧種のカワツルモが繁茂し、魚たちが豊富な栄養を得て元気に育っている。最近では、この地ならではの自然を見に、海外からゲストが訪れる機会も増えた。
「今、そうした方々に向けたプログラムも準備しています。国内外の多くの方に、海と森の壮大な循環を体感してもらいたいと思っています」
※『Nile’s NILE』2025年11月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています