
北海道のほぼ中央に位置する旭川から北へ50キロ――ここには“羊のまち”士別がある。
大雪山系の地下でじっくり寝かされた雪解け水には豊富なミネラル成分が宿るため肥沃な土地となるこの辺りはかつて農業も畜産業も盛んだった。しかし、この地も日本の農業が抱える問題から逃れられず後継者がいなくて廃業に追い込まれる農家も少なくない。そうした中、もう一度かつての活気あるまちにするために士別市では「サフォークランド士別プロジェクト」を設立し6年前から「サフォーク羊によるまちづくり」に力を入れている。
このとき地元企業として協力してほしいと白羽の矢が立ったのがしずお建設である。
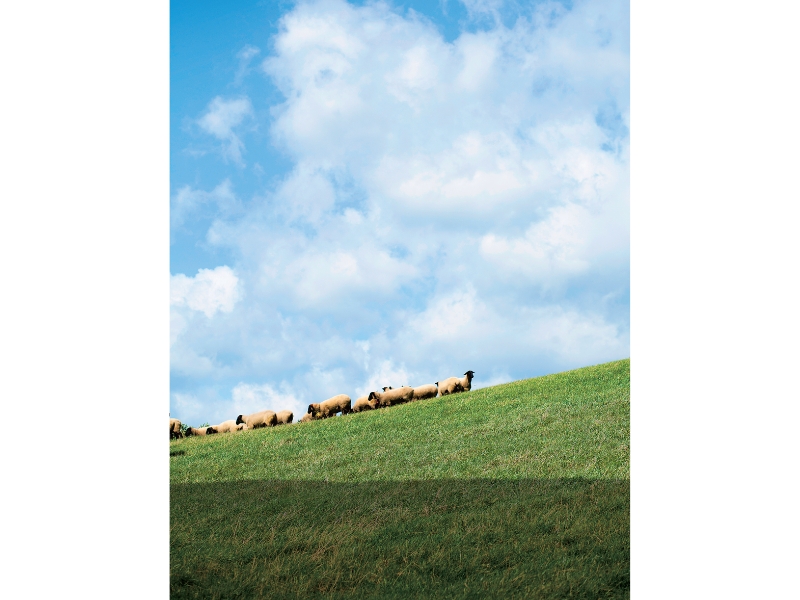
「農業生産法人として私が社長を務めるしずお農場の母体はしずお建設です。初代社長である義父佐藤静男はつるはし1本でここ士別へ入植した人。その後国道や河川工事の公共事業も請け負える建設会社にまで大きくしました。ここまでできたのは“士別のお陰”と市に恩返しするつもりで羊プロジェクトに賛同し農場を始めました」
と当時を振り返るのはしずお農場の今井裕社長だ。
「周辺の農家さんに羊の飼い方を聞いたり焼尻島で長年サフォークを育てている大井公世さんのところへ若いスタッフを連れて研修に行ったりして一から学びました」これが5年前の話。当時25頭だった羊は現在600頭にまで増えた。
これからは育てるだけじゃダメ
「一次産業だけの酪農や農業には限界があります。二次産業で消費者が使いやすいよう加工し三次産業としてのサービスも含めた販売までをしないと特に羊はダメです。家畜として認定されていないから畜舎を建てるにも助成金は出ないし国からの支援もありません」
と北海道ですら羊が飼いにくい状況にあると指摘する今井さん。
そこでしずお農場では自社で食品加工部門を設け屠殺場へ出して戻ってきた半身の羊肉をパーツごとに分けることで商品として販売。さらに「CellsAliveSystem」(細胞が生きている)を採用した電磁冷凍庫を導入しパーツごとの肉のほか内臓も冷凍している。「CAS」冷凍庫のメリットは細胞が破壊されず解凍後には鮮度のよい生肉をそのままの味わいで再現できる。これを武器に独自で販路を拡大してきた。
そして“脱ジンギスカン”を目指し「士別産サフォーク」のブランド化を図ろうと士別独自のラムの基準を設け品質を一定化。出荷販売はしずお農場が市内5つの農家の分も取りまとめている。羊に与える飼料も統一し士別ブランドの品質を保つようにしている。
異業種からめん羊事業へ。わずか5年で士別産サフォークのブランド化を大きく前進させているしずお農場。これからも先代から受け継いだ機動力を活かし士別産サフォークを広めていくに違いない。

※『Nile’s NILE』2011年10月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。






















