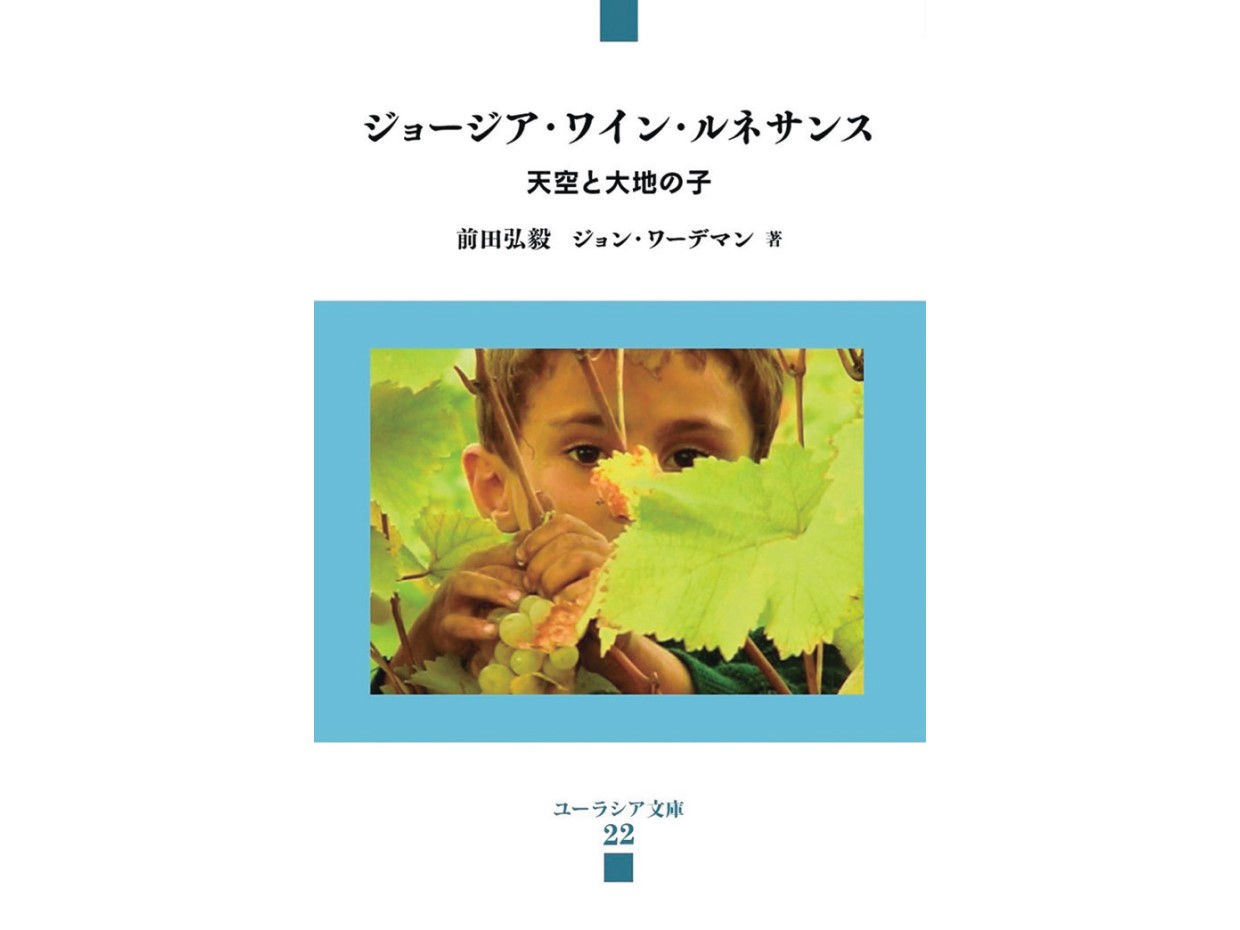
前田弘毅、ジョン・ワーデマン著/ユーラシア文庫・群像社/2025年4月刊/990円
まず、ナチュラルワインの話から入ろう。今年4月、OIV(国際ブドウ・ワイン機構)が発表したレポートによれば、2024年の世界のワイン生産量と消費量は過去60年で最低の水準に落ち込んだ。アルコール離れは確実に進行している。にもかかわらず、拡大傾向にあるのがナチュラルワインと言われる。
ナチュラルワインとは、農薬や化学肥料に頼らずに育てたブドウを、市販の培養酵母ではなく醸造所内やブドウの皮に存在する野生酵母で発酵させ、酸化防止剤を使用せず、無濾過(ろか)で瓶詰めした、いわば昔ながらの製法によるワインを指す。口当たりの良いジューシーな味わいや染み入るようなのど越しが特徴。最近ではワインにはまったきっかけがナチュラルワインという「ナチュール・ネイティブ」も。彼らは20~30代と若く、支持の理由にサステナビリティがあるとされるだけにナチュラル市場の伸長は続くと予測される。
ナチュラルワインが日本で流通し始めたのは2005年前後。当初はビオワイン、オーガニックワイン、自然派ワイン、ヴァン・ナチュールなどさまざまに呼ばれていた。「ナチュラルワイン」の呼称で統一されてくると、雑誌が相次いで特集―『Meets』2021年10月号「ナチュラルワインのはじめかた。」、『BRUTUS』2022年6/1号「ナチュラルワイン、どう選ぶ?」―を組み、街場への浸透を印象付けた。
そんなナチュラルワインを理解するうえで忘れてならないのが、今回の本題、ジョージアワインである。もし、ワイン好きなら、5、6年前から赤でも白でもない「オレンジワイン」というカテゴリーができていることにお気付きだろう。オレンジワインこそがナチュラルワインの普及によって形成されたカテゴリーであり、そのルーツがジョージアなのである。地中に埋めたクヴェヴリと呼ばれるかめの中で、果汁・果皮・果肉・果梗・種ごと野生酵母で醸すことによって、果皮の色素が溶出してオレンジ色や琥珀(こはく)色になる。ナチュラルワインを牽引(けんいん)してきた造り手たちがこのジョージア伝統のクヴェヴリ製法にインスパイアされたところからオレンジワインは国際市場に広まったのだった。
本書は、世界最古(8000年!)のワイン文化の地にして独自の製法で琥珀色輝くワインを生み出した同国の醸造の歴史をひもときつつ、世界中から注目を集める現代のジョージアワインに光を当てる。


















