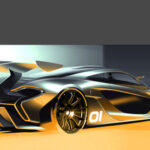21世紀を迎えて十余年。自動車業界では100年を一つの区切りとする、さまざまなアニバーサリーが行われている。多くの老舗カーメーカーが誕生し、世界的なカーレースが始まったのが、1900年代初頭となるからだ。
インディアナポリス500マイルレースとして知られる通称”インディ500”が初開催されたのも1911年である。
そして、この時期もう一つ50周年アニバーサリーも多く耳にする。さかのぼること1960年代。まさにめまぐるしく発展するモータリゼーションのさなか、数々の魅力的なクルマが誕生した。
ここで紹介するフォードのマスタングもまたそんなタイミングで生を受けた一台。誕生日は1964年4月17日。ニューヨークの博覧会会場で大々的にお披露目されると瞬く間に注目を集めた。
資料を読み込めば、マスタングが爆発的なヒットになったのは、納得できる。それまでにない2+2の四人乗りスポーツカーを、コンパクトで、さらに低価格なものとして実現してみせたのだ。
しかも、ターゲットは明白。第2次世界大戦以降のベビーブーマーだ。より巨大化するマーケットに向けて、彼らが欲するであろうシロモノをプロファイルし、そこにマスタングを投げ込んだ。
仕掛けたのは当時フォード社の副社長に就いていたリー・アイアコッカ氏。マスコミ対応にもたけていた彼は、発売前のマスタングをメディアに貸し出し、世間をあおったとも伝えられる。商品開発から販売促進まで、なかなかのやり手だったことは間違いない。

さてさて、それから50年。マスタングはその火を消すことなく昨年4月にアニバーサリーを迎えた。すると、そのタイミングでフルモデルチェンジし、6世代目となる新型車をデビューさせた。
写真をご覧いただきたい。これがそのクルマ。しかも、50周年を記念した限定車である。日本には350台のみあてがわれた。

目玉は、この二枚目的なスタイリング。60年代に活躍した初代マスタングをモチーフにしながら、それを現代的にアレンジした。LEDを使ったライトまわりや複雑な面構成のグラマラスなボディーラインを実現しながらも、全体的な印象はキープしている。
そしてまたエンジンもトピックの一つ。何と積まれたのは2.3リッター直4ターボ。第3世代以来の4気筒エンジンである。
が、これが至って今日的。フォードが得意とする高効率エンジンは省燃費にたけながらも、絶大なパワーを発揮してくれる。314馬力が、ついにV6エンジンの性能を上回ったのだ……。
といった内容のマスタング。ネーミングと、そこからくるイメージは踏襲されたものの、中身は最新。なるほど、今度のマーケティングも完璧である。
●Mustang 50 YEARS EDITION
ボディー:全長4790mm╳全幅1920mm×全高1380mm
エンジン:2.3ℓ 直列4気筒DOHC
最高出力:231kW(314ps)/ 5500rpm
最大トルク:434Nm(44.3kg・m)/ 3000kg
駆動方式:FR
トランスミッション:6速AT
価格:4,650,000円
●フォードお客様相談室 フリーダイヤル0120-125-175
※『Nile’s NILE』に掲載した記事をWEB用に編集し再掲載しています