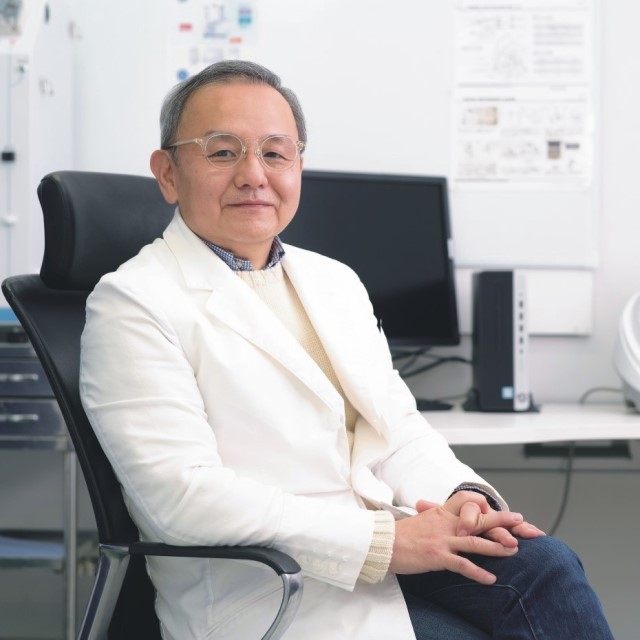人間、誰しも誤りや勘違いというものはある。しかし「それにしてもこれはないだろう」という出来事が最近、我が国で起きた。それは安倍政権による「経営者は賃金を上げよ」という声高な要求である。実に笑止としか言いようがない。
なぜか。安倍政権は発足より前から通称「アベノミクス」なるものを喧伝してきた。これはいかに高名な先生の名前を出したところで、とどのつまり「マネーを刷ってばらまけば景気は良くなる」という議論だ。これを唱える学者たちは一般にリフレ派と言われている。一方、このリフレ派と「百年戦争」とでもいう論争を繰り広げてきた先生たちがいる。彼らは「マネーがばらまかれても結局は銀行や大企業にたまるだけ。消費を促し、景気を良くするには名目賃金を引き上げるしかない」と主張してきた。
ここでどうして安倍政権の対応が笑止なのかというと、前者と後者を接ぎ木したからである。つまり口先介入による日本株高を実現したと思ったらば、今度は賃金を引き上げろと言い出したのである。それぞれの議論にはそれなりの根拠がある。それらをすっ飛ばして「足して二で割る」というのだから、いい加減さにも程があるというわけなのだ。事実、賃金は上げられていない。
景気を良くするためには多くの人たちが職を得ればいいし、同時にたくさんのモノが売れるようになればいいのである。小難しいことは言わずとも、そんなことは青二才の経済学徒でも分かることだ。ところが政治もアカデミズムも「バカの壁」に入ってしまい、どうしたらいいのか分からないままでいる。
「そういうお前はどうなのか?」
――そんな声が聞こえてきそうだ。無論、こう言う以上、私の懐にはいくつかの処方箋がある。その一つが我が国における首都高速の地下化という一大プロジェクトである。これは単なる思い付きではない。国土交通省において「首都高速の再生に関する有識者会議」なるものが立ち上げられ、昨年9月には提言書が取りまとめられたという立派な国家的プロジェクトだ。
我が国の都心で目立つのは、建設後50年近くも経過している醜く老朽化した首都高速道路である。これを地下化すれば美観も確保される上、空いた土地を有効利用できる。ボストンやソウルでの先例を見れば、公共事業として持つ経済効果が抜群であることは明らかであり、多くの人たちが職を得られることにもつながる。肝心要なのはもちろん「誰がカネを出すのか」という点なわけだが、これとて基本的には民間資金を活用し(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)、政府は「いざとなったら何とかするから」と保証を付ければそれでよいのである。後は国民が少しだけ我慢をして首都高速道路の有料化持続を許せば、そこで捻出されたマネーで着実に返していけばいい。首都高速道路が「償還力」抜群なのは誰の目にも明らかなはずだ。
ところが関係者いわく「政治家たちが一切動こうとしない」のだという。経済にはうとい安倍総理(あの「アベノミクス答弁」を聞いていれば明らかだ)はまだしも、それ以外の閣僚たちも「聞き置く」だけで動こうとはしない。一体何を恐れているのか。戦後間もなくのインフラ投資が原則として米欧マネーで行われたのであれば、彼らも裨益する形でスキームを組めばよい。その力が政治にないというのであれば、誰か誠意ある我が国の民間人に指示すればいいだけである。それをしないで何が「政治」であり、「選挙」だというのか。「自分の懐に入らないから」などと考えていないという証しのためにも、安倍総理は今こそ自ら動くべきではないか。この「美しい国」日本のために。
原田武夫(はらだ・たけお)
東京大学法学部在学中に外交官試験に合格し、外務省に入省。12年間奉職し、アジア大洋州局北東アジア課課長補佐(北朝鮮班長)を最後に2005年に自主退職。2007年から現職に。「すべての日本人に“情報リテラシー”を!」という思いのもと、情報リテラシー教育を多方面に展開。自ら調査・分析レポートを執筆すると共に、国内大手企業等に対するグローバル人財研修事業を全国で行う。近著に『ジャパン・シフト 仕掛けられたバブルが日本を襲う』(徳間書店)『「日本バブル」の正体~なぜ世界のマネーは日本に向かうのか』(東洋経済新報社)がある。
https://haradatakeo.com/