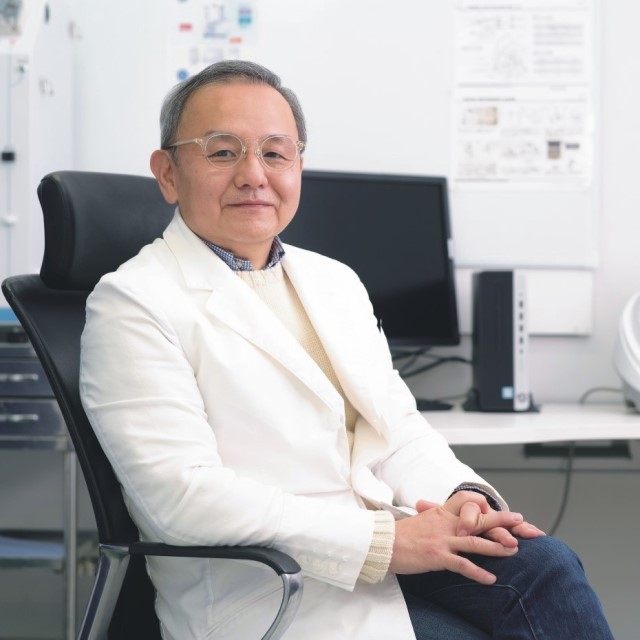実は昨年、2016年8月からグローバル経済は決定的な形で変化し始めている。その奥底において、これまで表立ってカウントされてこなかった莫大な量の金塊が現金化され始めたからなのであるが、それに加えて今年2017年6月になり、今度は表の世界でも重大な変化が生じた。「円高基調における我が国固有の資産バブル展開」としての“日本バブル第2弾”がついに始まったのである。
「一体何のことを言っているのか。我が国において株価は時に騰がることはあっても、下がることもある。要するに一進一退なのであって“バブル”などというものからは程遠いのではないか」。そんな言葉が読者の口からは聞こえそうである。だが、今回は断然“バブル”なのだ。なぜそう言えるのであろうか。
私たちが普段、忘れていること。それはいわゆる「平成バブル」以降に発生したバブル局面においては、常に「円高」が特徴的であったという事実だ。これは「マーケットにおける一般常識」を刷り込まれている方々からすれば、やや驚きかもしれない。なぜならば、この「一般常識」ではこう語られるのが常だからだ。
「我が国の株価、とりわけ日経平均株価として示される株価指標は、円安になると上昇する。したがって株価を上昇させたいならば、円安に誘導するのが常道なのであって、円高ではむしろ株価が下がってしまう」
これは表層的には正しい。だがマーケットの深層においては、正しい見解ではない。
まず「円高である」のはイコール、我が国が選ばれているからである。「円高は悪の根源」といった見解が一般的だが、普通、マーケットで人気があるからこそ、そのモノの値段は高くなるのである。したがって、この大原則に則(のっと)るならば、円高は通貨としての日本円、さらにはその背後にあって実質的な存在である我が国ニッポンそのものが、マーケットの参加者によって選ばれていることを意味しているのだ。
そしてその結果、マーケット参加者の多くが日本円を持つに至るのであれば、次に「この日本円をもって何を買おうか」という話になるのは必然なのである。我が国のマーケットに数多くの売り物があることは事実だ。しかしよくよく考えてみると、とりわけ外国からやって来る投資家たちにとって、売買しやすいものは限られている。その一つが株式だ。だからこそ株価がむしろ上昇するというわけなのである。
同時にもう一つ見過ごせない理由がある。それは我が国において「バブル」が発生するのは、決まって政府当局がそのように誘導している時なのである。「平成バブル」の時もそうであった。まず為替レートについて円高・ドル安になることを容認する「プラザ合意」に我が国の政府当局は同意した。それによって我が国経済が不振になることを理由に、今度は大規模な緩和策をとったのである。その結果、マネーが巷にあふれ、バブルとなったのだ。
それでは現在はどうかというと、まさにこうした意味での「官製バブル・アゲイン」が仕掛けられている。不動産投資信託(REIT)に対する融資は、これまで我が国においてメガバンクだけが行ってきた。そうした中で今年、2017年5月末からメガバンクたちはこれを証券化し、地方銀行など他の金融機関に対して売りさばくという動きを見せ始めたのである。不動産バブルを惹起させようと全国で集金作業に取り掛かり始めたわけだ。
ちなみにこの証券化による仕掛けは、かのリーマン・ショックの直前まで米国で横行していたものに他ならない。無論、金融当局による指導がこうした動きの背後には見え隠れする。
これでお分かりになったのではないか。今、我が国政府当局はこぞって「官製バブル」を仕掛け始め、それを知った外国勢は一斉に日本円を買い、「円高」になっている。“日本バブル第2弾”が始まったのだ。円安誘導によるアベノミクスの時代は終わった。「その主」もまた首班の座から、去る日はそう遠くはあるまい。
原田武夫 はらだ・たけお
元キャリア外交官。原田武夫国際戦略情報研究所代表(CEO)。情報リテラシー教育を多方面に展開。2015年よりG20を支える「B20」のメンバー。
※『Nile’s NILE』に掲載した記事をWEB用に編集し再掲載しています